
プリウスミサイルは不謹慎なのか?実際の事故率が高いわけではなく、販売台数の多さなどによる印象が主な理由ですが、事故被害者を揶揄する不謹慎な言葉です。ネット上で見かけるこの言葉について、あなたもその背景にある多くの疑問や複雑な感情をお持ちかもしれません。
この記事では、言葉の正確な意味や元ネタを解き明かし、なぜ多いと感じられるのか、その真相に迫ります。プリウスにまつわる危険運転の評判や、なぜイメージ悪いと言われるのか、特に高齢者ドライバーによる事故との関連性にも深く言及します。
さらには、客観的なデータに基づいた安全性能や、メーカーとしてのトヨタの見解、そして一部で囁かれる乗り心地悪いという話は事実なのかも検証します。社会に大きな衝撃を与えた飯塚幸三氏の事故が与えた影響も含め、この問題の全体像を多角的に解説していきます。
- 「プリウスミサイル」という言葉の正確な意味と由来
- 事故が多いと言われる客観的な理由とデータの真偽
- トヨタの公式見解とプリウスが持つ本当の安全性
- 言葉がなぜ不謹慎とされ、今後どう向き合うべきか
目次
プリウスミサイルは不謹慎という言葉の背景

- プリウスミサイルは不謹慎という声
- 言葉の詳しい意味と元ネタを解説
- なぜ多いと感じるのか?その背景
- プリウスは危険運転多いという噂
- 事故の具体例
- 高齢者事故の関連性
- 飯塚幸三の事故
プリウスミサイルは不謹慎という声
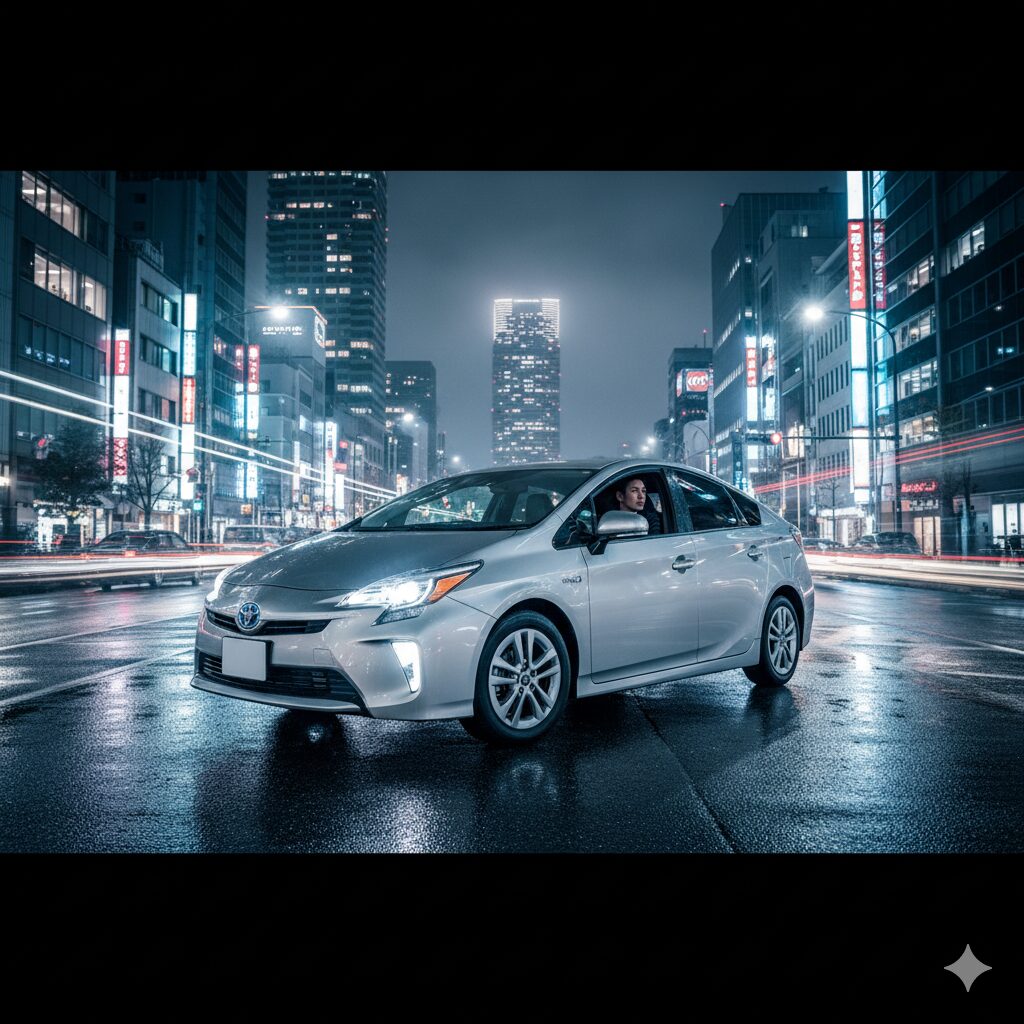
「プリウスミサイル」という言葉は、その語感のインパクトとは裏腹に、多くの人から不謹慎であると厳しい目が向けられています。その最大の理由は、この表現が実際の交通事故、つまり人の命や身体が危険に晒された現実の悲劇を、軽々しく揶揄している点にあります。
言うまでもなく、交通事故の被害者やそのご家族、関係者にとっては、人生を一変させてしまうほどの計り知れない苦痛を伴う出来事です。それを「ミサイル」という攻撃的で非人間的な言葉で表現し、まるでゲームかのように笑いの対象とする行為は、社会的な倫理観に照らして問題があると考える人が多いのは当然と言えるでしょう。特にSNSなど、不特定多数の目に触れる場所でこの言葉が安易に使われるたびに、「被害者や遺族の気持ちを考えていない」「人の不幸をネタにするな」といった強い批判が巻き起こります。
言葉の重みと二次被害
たとえ発言者に直接的な悪意がなかったとしても、言葉は受け取る側によってその意味合いが大きく変わります。特に人の生死に関わる事柄を軽い冗談として扱う風潮は、被害者を再び傷つける「二次被害」を生み出しかねません。さらに、プリウスを安全に運転している多くの一般ドライバーにとっても、このようなレッテル貼りは迷惑千万であり、深刻な風評被害につながっています。
このように、単なるネットスラングとして片付けるにはあまりにも重い社会的背景が存在するため、「プリウスミサイル」という言葉の使用には、多くの人々が強い抵抗感と嫌悪感を抱いているのです。
言葉の詳しい意味と元ネタを解説

「プリウスミサイル」という言葉の意味は、トヨタの人気ハイブリッドカー「プリウス」が、コンビニエンスストアや商業施設、あるいは歩道などに突っ込む事故を指す、極めて皮肉のこもったインターネットスラングです。ドライバーの意図に反して急加速し、まるでミサイルのように一直線に目標物へ突進していく様子から、この揶揄的な表現が生まれました。
明確な元ネタを一つに特定するのは困難ですが、この言葉がインターネット上で広く拡散する大きなきっかけとなったのは、間違いなく2010年代後半から社会問題として注目され始めた、高齢ドライバーによるアクセルとブレーキの踏み間違い事故の多発です。その中でも特に、2019年に発生し、社会に大きな衝撃を与えた「池袋暴走事故」が、この言葉の認知度を決定的に高めたと言われています。
スラングの誕生と変遷
元々は2000年代後半から、一部のネット掲示板やSNSなどの匿名コミュニティで、プリウスの特異な運転挙動や事故を皮肉る際に使われ始めた言葉でした。それが痛ましい事故報道がメディアで繰り返されるうちに、より広い層へと知られるようになり、特に池袋暴走事故以降は、高齢者ドライバー問題の象徴的な言葉として定着してしまった経緯があります。
言ってしまえば、プリウスミサイルとは、特定の車種が関わる事故を誇張し、ブラックユーモアとして消費するネット文化の中から生まれた言葉なのです。しかし、その根底には、高齢化社会における交通問題という、決して笑い事では済まされない深刻な課題が横たわっています。
なぜ多いと感じるのか?その背景
| 「プリウスの事故が多い」と感じられる心理的・社会的要因 | |
|---|---|
| 要因①:母数の多さ | 圧倒的な販売台数により、街中で見かける機会が多い。そのため、事故が発生した際にプリウスである確率が自然と高くなる。 |
| 要因②:報道の影響 | 衝撃的な事故が起こると、メディアが車種名を繰り返し報道。これにより「プリウス=事故」という強力なイメージが刷り込まれる。 |
| 要因③:ドライバー層 | 燃費やサイズ感から高齢者層に人気が高い。加齢による運転能力の変化と事故が結びつけて考えられやすい。 |
| 要因④:確証バイアス | 一度「危ない」という先入観を持つと、その情報を裏付ける事故例ばかりが記憶に残り、印象がさらに強化される。 |
プリウスの事故が「なぜ多い」と世間で感じられているのか、その背景には複数の要因が複雑に絡み合っており、決してプリウスという車種の機械的な欠陥だけが原因ではありません。
最大の理由は、プリウスの圧倒的な国内販売台数にあります。プリウスは1997年の登場以来、ハイブリッドカーの代名詞として爆発的な人気を誇り、一般社団法人 日本自動車販売協会連合会の統計によれば、長年にわたり新車販売台数ランキングの上位に君臨してきました。2017年時点で国内累計販売台数は400万台を超えており、街中で見かける機会が他の車種に比べて圧倒的に多いのです。
この「母数の多さ」が、「またプリウスか」という印象を人々に与える直接的な原因です。母数が大きければ、それに比例して事故に遭遇する絶対数も多くなるのは統計上の必然と言えます。
これは「利用可能性ヒューリスティック」という心理効果の一例です。衝撃的なニュースなどで頻繁に目にする情報は、実際の発生確率以上に「よくあること」だと錯覚しやすいのです。プリウスの事故報道は、まさにこの典型例ですね。
さらに、プリウスが燃費の良さや扱いやすいサイズ感から、運転に慎重さが求められる高齢者層から高い支持を得ている点も見過ごせません。これらの要因が複合的に絡み合い、プリウスの事故が社会的に「目立ちやすい」状況を生み出しているのです。
プリウスは危険運転多いという噂
| 危険運転の噂に繋がるプリウスの主な特性 | |
|---|---|
| 特性①:静粛性 | モーター走行時は非常に静かなため、エンジン音で速度を体感しにくい。無意識のうちに速度超過になる可能性がある。 |
| 特性②:鋭い加速性能 | モーターアシストにより、アクセルを軽く踏んだだけでも力強く加速する。この感覚に慣れないと急発進しやすい。 |
| 特性③:特殊なシフトレバー | 操作後にレバーが定位置に戻るため、視覚的にシフト位置を確認しにくい。特に慣れないドライバーの誤操作を誘発する可能性がある。 |
「プリウスは危険運転多い」という噂は、ネット上だけでなく、日常的に車を運転するドライバーの間でも囁かれることがあります。この少し不名誉なイメージが定着してしまった背景には、プリウスが持つ特有の運転感覚が大きく影響しています。
静かすぎる走行音と鋭敏な加速性能
プリウスは世界をリードするハイブリッドカーであり、特に発進時や低速走行時はエンジンを停止させ、モーターのみで走行します。そのため走行音が非常に静かです。従来のエンジン車に慣れているドライバーにとっては、エンジン音で速度を体感することが難しく、知らず知らずのうちに想定以上のスピードが出てしまうことがあります。
また、モーターによる強力なアシストは、アクセルレスポンスを非常に鋭敏にします。軽く踏んだだけでも力強くスムーズに加速するため、この感覚に慣れないうちは「急発進しやすい」「飛び出しそうで怖い」と感じる人も少なくありません。
慣れが必要な特殊なシフトレバー
2代目以降のプリウスに長らく採用されてきた電子式の「エレクトロシフトマチック」は、操作後にレバーが自動で中央の定位置に戻る特殊な仕様です。従来のAT車のようにレバーの位置でシフトポジションを確認できないため、特に乗り慣れないドライバーや高齢者にとっては直感的でなく、「D(ドライブ)」と「R(リバース)」の入れ間違いといった誤操作を誘発しやすいと長年指摘されてきました。
これらの要因が複合的に作用し、「プリウスの運転マナーが悪い」というよりも、「ドライバーの意図に反して危険な運転状況に陥りやすい特性を一部持っている」と捉えることができます。これが結果として「危険運転が多い」という噂につながっているのです。
事故の具体例

「プリウスミサイル」という過激な言葉を裏付けるかのように、社会に大きな衝撃を与えた事故の具体例が残念ながらいくつか存在します。これらのセンセーショナルな事件報道が、プリウスに対する特定のネガティブなイメージを決定的なものにしてしまいました。
静岡スーパーマーケット突入事故 (2021年)
2021年、静岡県内のスーパーマーケットで、80代の女性が運転するプリウスが駐車場で急加速し、店舗のガラスを突き破って店内に突っ込むという衝撃的な事故が発生しました。報道によると、運転者は「アクセルを軽く踏んだだけで一気に動いてしまった」「ギアがどこに入っていたのか分からなかった」という趣旨の証言をしており、高齢による判断力の低下とプリウスの操作性への不慣れが複合的に絡み合った事故と見られています。
著名人の事故被害報告
人気配信者である加藤純一氏が、自身の妻が横断歩道を横断中にプリウスに衝突される事故に遭ったと配信で語ったことも、このイメージを強める一因となりました。影響力のある著名人が被害者としてプリウスの名を挙げたことで、「やはりプリウスは危険な車だ」という印象がインターネット上で再び強く拡散される結果となったのです。
これらの事故は、いずれも調査の結果、プリウスという車種そのものの機械的な欠陥が原因とされたわけではありません。しかし、メディアで繰り返し報道されることで、「プリウス」と「予期せぬ暴走事故」というイメージが人々の間で強く結びついてしまったことは否定できません。
高齢者事故の関連性

プリウスと高齢者事故の関連性は、この問題を語る上で避けては通れない、非常に重要なテーマです。プリウスが「高齢者の事故車両」という不名誉なイメージを持たれるようになったのには、統計的・社会的な背景が存在します。
まず、トヨタの公式情報や販売データが示す通り、プリウスは利用者の年齢層が比較的高く、特に60代以上のシニア層から長年にわたり高い支持を得ています。子育てを終えた世代が、優れた燃費性能や日本の道路事情に合った扱いやすいサイズ感、そしてトヨタブランドへの信頼感からプリウスを選ぶケースが非常に多いのです。
その一方で、警察庁の運転免許統計によれば、75歳以上の後期高齢者ドライバーの数は年々増加傾向にあります。そして、加齢に伴う身体能力や認知機能の低下は、運転操作に影響を及ぼすことが科学的にも証明されています。
加齢による運転能力の変化
- 反応速度の遅延:危険を発見してからブレーキを踏むまでの時間が長くなる。
- 判断力の低下:複数の情報を同時に処理する能力が衰え、複雑な交通状況で混乱しやすくなる。
- 注意力の低下:注意を多方面に配分することが難しくなり、危険の見落としが増える。
これらの避けがたい能力低下が、プリウス特有の静粛性(速度感の喪失)や特殊なシフト操作(誤操作の誘発)と組み合わさった時、アクセルとブレーキの踏み間違いといった致命的な操作ミスを引き起こすリスクが高まると専門家は指摘しています。つまり、「高齢者」と「プリウス」という二つの要素が掛け合わさることで、社会的に事故が目立ちやすくなるという構造が生まれてしまっているのです。
飯塚幸三の事故
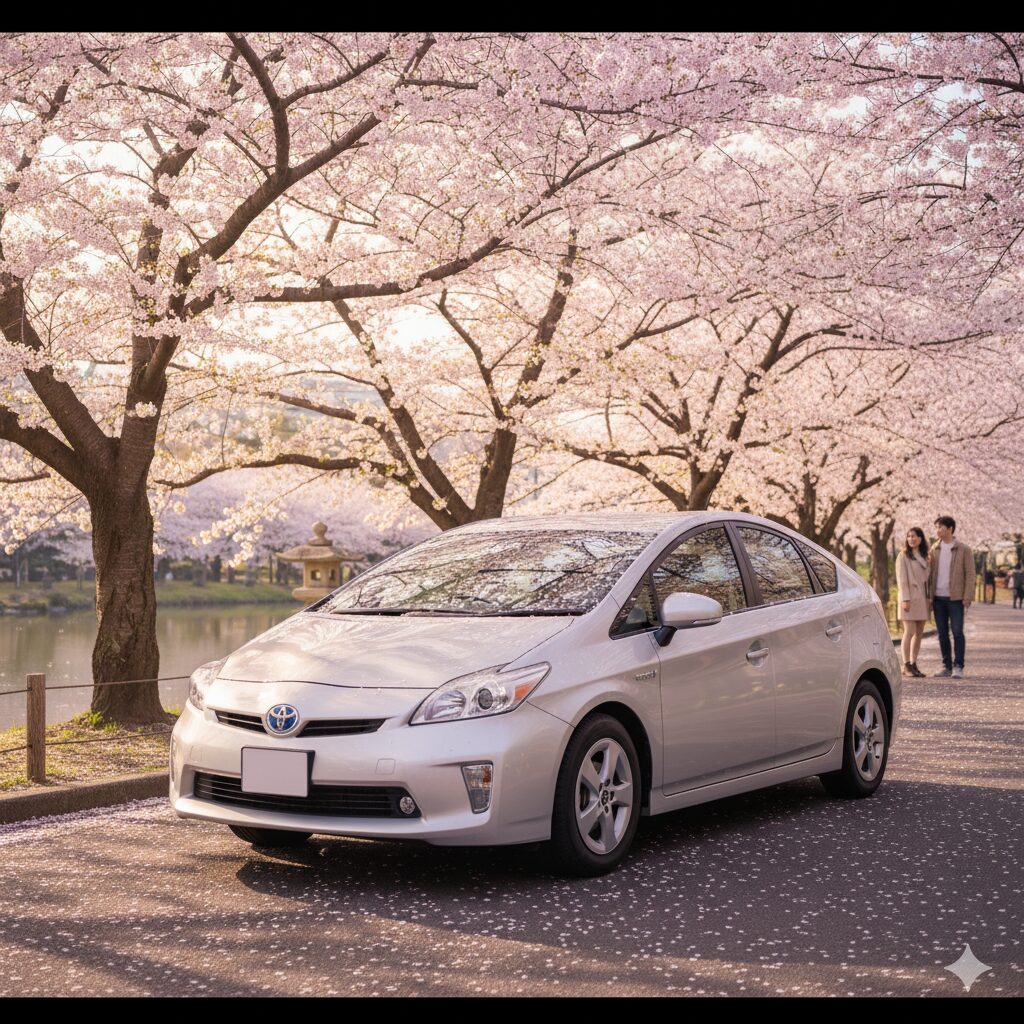
元高級官僚である飯塚幸三元院長が起こした「池袋暴走事故」は、「プリウスミサイル」という言葉の持つ負のイメージを日本社会に決定づけた、あまりにも象徴的な事件です。
2019年4月19日、当時87歳だった飯塚氏が運転する2代目プリウスが、東京・東池袋の繁華街で赤信号を無視して複数の交差点に猛スピードで進入し、多くの歩行者や自転車を次々とはねました。この暴走の結果、自転車に乗っていた31歳の母親と3歳の娘の尊い命が奪われ、運転者とその同乗者を含む10人が負傷するという、大変痛ましい大惨事となりました。
事故後の捜査や刑事裁判において、飯塚氏は一貫して「ブレーキを踏んだが効かなかった」「車に何らかの異常があった」と、運転ミスではなく車両の欠陥が原因であると無罪を主張しました。しかし、事故車両に残されたイベントデータレコーダー(EDR)の解析などから、事故直前にブレーキペダルが操作された記録はなく、むしろアクセルペダルが強く踏み続けられていたことが客観的なデータで判明しました。最終的に、東京地方裁判所は車両の異常という主張を退け、運転者の操作ミス、すなわちアクセルとブレーキの踏み間違いが事故原因であると認定し、禁錮5年の実刑判決を言い渡しました(その後、上告せず刑が確定)。
この事件は、被告が元高級官僚であったことから「上級国民」という言葉がSNSでトレンド入りするなど、単なる交通事故に留まらない、社会の不公平感をも浮き彫りにする大きな社会問題へと発展しました。そして、「プリウス」という車種と「高齢者による制御不能な悲惨な事故」というイメージを、人々の記憶に消しがたく刻み込むことになったのです。
プリウスミサイル不謹慎問題の真相と結論
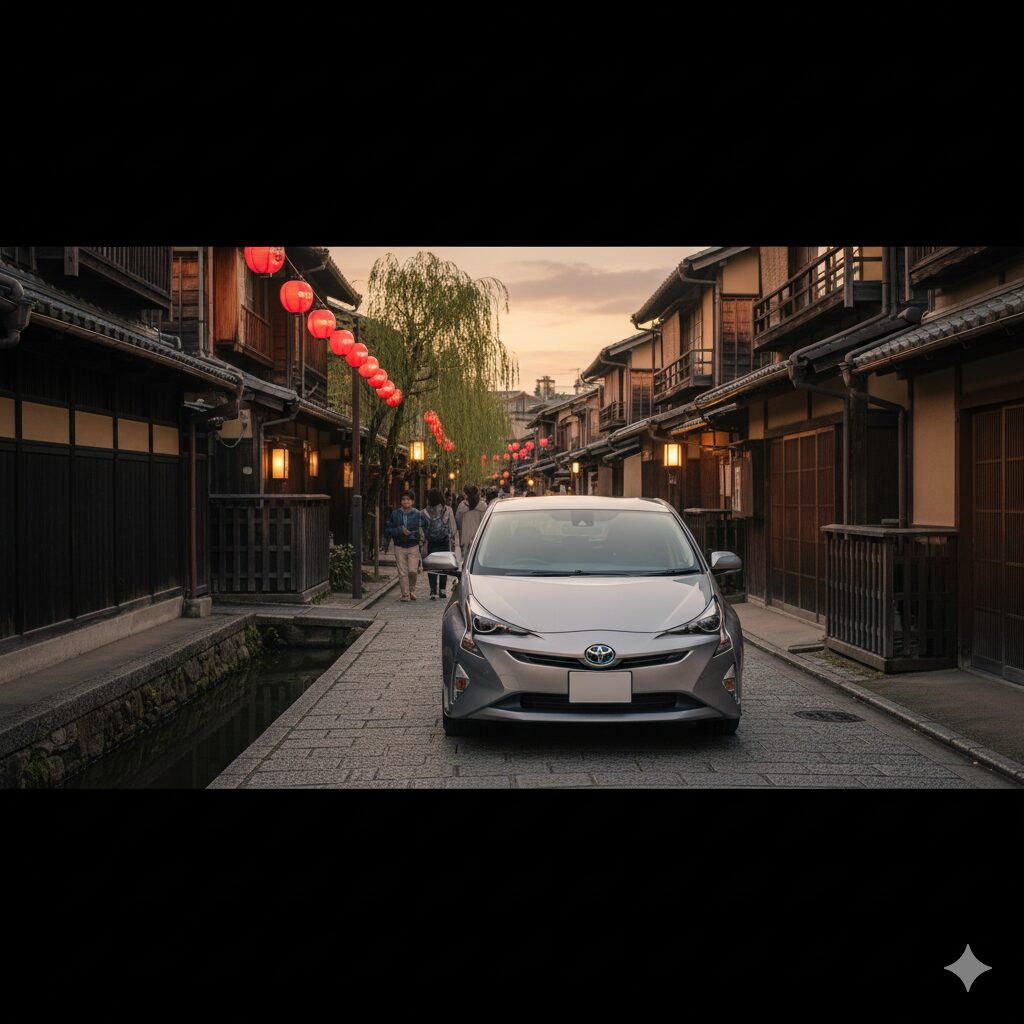
- 実際の事故率と事故理由
- データで見る安全性能
- 評判とイメージが悪い理由
- 乗り心地悪いと言われる理由
- プリウスミサイルへのトヨタの見解
- 結論:プリウスミサイルは不謹慎か
実際の事故率と事故理由

「プリウスは事故が多い」という世間に流布するイメージとは裏腹に、実際の事故率は、客観的なデータを見る限り突出して高いわけではありません。むしろ、イメージと現実の間には大きなギャップが存在します。
その根拠の一つが、自動車保険の保険料を算出する基準となる「型式別料率クラス」です。これは、車種ごとの事故リスクを過去の膨大な統計データから評価したもので、数値が高いほどリスクが高い(=保険料が高い)ことを意味します。4代目プリウスの料率クラスを見ると、他の一般的な国産コンパクトカーやセダンと比較しても決して高い数値ではなく、むしろ一部の項目では平均よりも低いクラスに設定されていることがわかります。
| 保険の種類 | 型式:ZVW50 | 型式:ZVW51 | 型式:ZVW55 |
|---|---|---|---|
| 対人賠償責任保険 | 10 | 8 | 3 |
| 対物賠償責任保険 | 8 | 5 | 6 |
| 人身傷害保険 | 9 | 9 | 3 |
| 車両保険 | 9 | 9 | 9 |
(出典:損害保険料率算出機構)※クラスは1~17段階評価
また、過去に国土交通省が実施した調査でも、プリウスの事故率は他のトヨタ車と比較して大差ないという結果が示されています。では、事故理由は何かというと、これまで述べてきた通り「圧倒的な販売台数による事故件数の多さ」や「ドライバーの年齢層の高さ」、そして「特有の操作性への不慣れからくるヒューマンエラー」といった、車本体の欠陥以外の複合的な要因が大きいと結論づけることができます。
データで見る安全性能
| Toyota Safety Senseの主要な安全機能 | |
|---|---|
| プリクラッシュセーフティ | 前方の車両や歩行者を検知し、衝突の危険があれば警報や自動ブレーキで被害を軽減する。 |
| レーントレーシングアシスト | 車線の中央を走行するようにステアリング操作を支援し、車線逸脱を防ぐ。 |
| レーダークルーズコントロール | 先行車との車間距離を一定に保ちながら追従走行し、運転負荷を軽減する。 |
| インテリジェントクリアランスソナー | アクセルの踏み間違いなどを検知し、駐車場などでの衝突被害を軽減する。 |
一部のネガティブなイメージとは全く対照的に、プリウスは客観的なデータで見ると、デビュー当時から常にトップクラスの安全性能を備えた先進的な車です。
現在のトヨタ車に広く展開されている先進安全技術パッケージ「Toyota Safety Sense」は、もちろんプリウスにも標準装備されています(※グレードや年式により機能は異なります)。これには、事故を未然に防いだり、被害を軽減したりするための高度な機能が含まれています。
Toyota Safety Senseの主な機能
- プリクラッシュセーフティ:ミリ波レーダーと単眼カメラで前方の車両や歩行者(昼夜)、自転車運転者(昼)を検知。衝突の危険が高まると警報を発し、ブレーキ操作を促します。万が一、ドライバーが反応できない場合は、自動でブレーキを作動させます。
- レーントレーシングアシスト:車線の中央を安定して走行するように、ステアリング操作の一部をアシストします。
- レーダークルーズコントロール:ミリ波レーダーで先行車を認識し、設定した速度内で適切な車間距離を保ちながら追従走行を支援します。
- インテリジェントクリアランスソナー:アクセルの踏み間違いや踏みすぎなどで起こる衝突を緩和し、被害の軽減に寄与するシステムです。駐車場などでのとっさの事故を防ぎます。
(出典:トヨタ自動車公式サイト プリウス安全性能)
さらに、プリウスは国が安全な車の普及を促進する「サポカーSワイド」の認定を受けています。これは、特に高齢ドライバーに推奨される、衝突被害軽減ブレーキ(対歩行者)やペダル踏み間違い時加速抑制装置などを備えた、極めて安全性能の高い車であることを国が認めている証です。
このように、プリウスは事故を「起こさせない」ための様々な先進技術が惜しみなく投入されている車種であり、決して「危険な車」ではないことが客観的なデータから明確に分かります。
評判とイメージが悪い理由

クラス最高レベルの安全性能を備え、実際の事故率も突出していないにもかかわらず、なぜプリウスの評判とイメージが悪い理由がこれほどまでに定着してしまったのでしょうか。その答えは、車の性能そのものではなく、主に人間の心理と情報伝達の仕組みにあります。
最大の要因は、やはり衝撃的なメディア報道とSNSによる爆発的な情報拡散です。特に「池袋暴走事故」のような、社会の関心が高い悲惨な事件が発生した際、ニュースでは視聴者の注意を引くために繰り返し「プリウス」という具体的な車種名が報じられました。これにより、「プリウス=高齢者による危険な暴走事故を起こす車」という、非常に強烈なネガティブ・イメージの刷り込みが行われてしまったのです。
これは「確証バイアス」という心理作用も関係しています。一度「プリウスは危ない」という先入観を持ってしまうと、その考えを支持する情報(プリウスの事故ニュースなど)ばかりが目につき、逆にそれを否定する情報(安全性能のデータなど)は無視しやすくなるのです。
一度定着してしまった悪いイメージは、SNS上で「プリウスミサイル」のようなキャッチーなスラングと共に、面白おかしく、あるいは悪意を持って再生産され続けます。その結果、客観的なデータや事実よりも、感情に強く訴えかける衝撃的な情報や偏見の方が、世間一般のイメージとして固定化されてしまったのです。これに「高齢者に人気の車種であること」や「特有の操作性」といった要素が補強材料として結びつき、プリウスに対する一方的で不当な評判が形成されてしまったと言えるでしょう。
乗り心地悪いと言われる理由
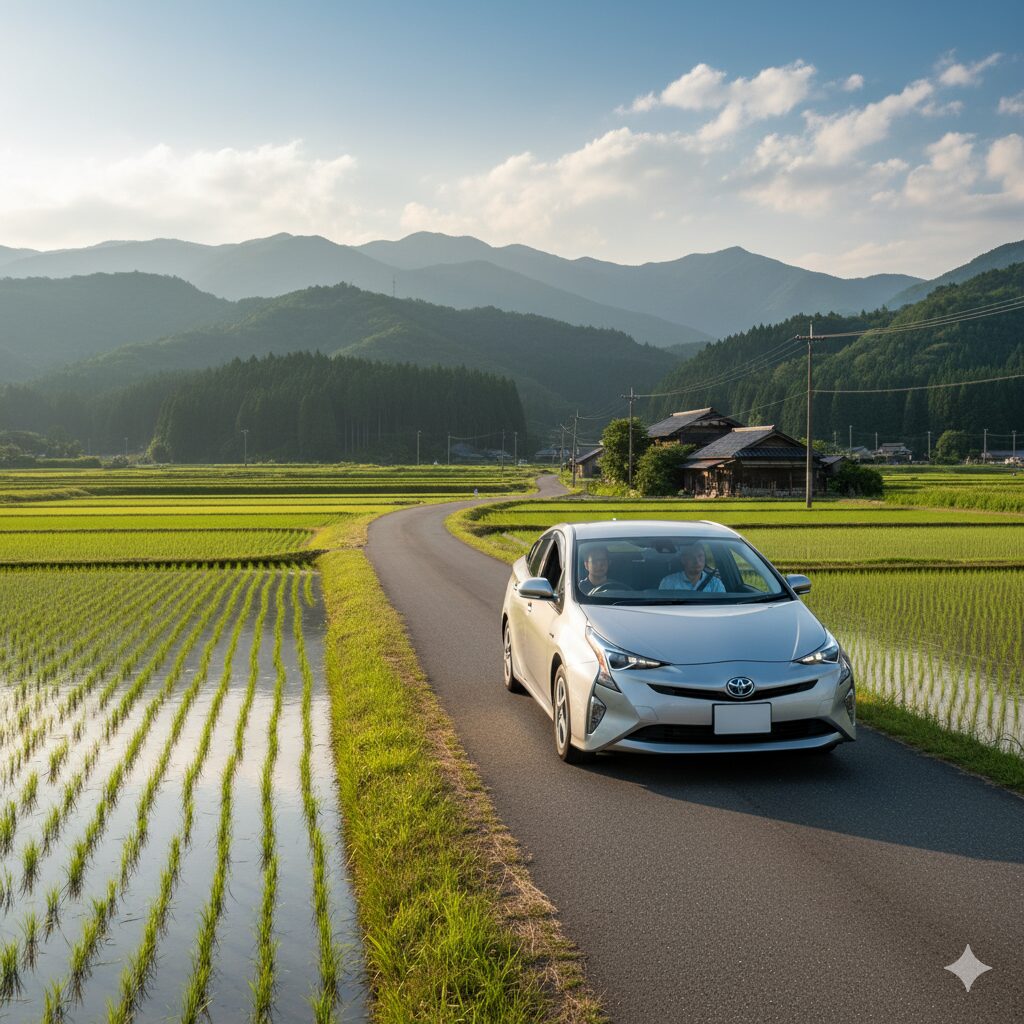
プリウスの評判を調べる中で、一部のドライバーから「乗り心地悪い」という声が聞かれることがあります。この評価には、特にプリウスの長い歴史の中でのモデルチェンジによる進化と、ハイブリッドカーならではの車の特性が深く関係しています。
旧モデル(特に30系)の乗り心地の評価
2009年に登場した3代目(30系)プリウスは、大ヒットモデルとなりましたが、乗り心地に関しては厳しい評価を受けることがありました。当時のトヨタ車の中では比較的サスペンションが硬めのセッティングで、路面の凹凸や段差を乗り越える際に、ゴツゴツとした直接的な突き上げ感を乗員が感じやすかったのです。この時代のプリウスに乗った経験が、「プリウス=乗り心地が硬くて悪い」というイメージの根源となっている可能性は高いでしょう。
新型モデル(50系以降)での飛躍的な改善
一方で、2015年に登場した4代目(50系)以降のプリウスでは、TNGA(Toyota New Global Architecture)と呼ばれる新世代のプラットフォームが採用され、乗り心地は劇的に改善されました。ボディ剛性が大幅に向上し、サスペンションがよりしなやかに動くようになったことで、路面からの衝撃を巧みにいなし、走行安定性と快適性が飛躍的に向上しました。さらに2023年に登場した最新の5代目(60系)では、19インチの大径ホイールを装着したモデルもラインナップされ、見た目のスポーティーさとは裏腹に、重厚で落ち着きのある上質な走りを実現しています。
静粛性がもたらす乗り心地への誤解
プリウスはハイブリッドカーの特性上、エンジン音が非常に静かです。そのため、普通のエンジン車では気にならないようなロードノイズ(タイヤが路面を転がる音)や風切り音が、相対的に目立って聞こえてしまうことがあります。この「特定の音が耳につく」という現象が、「乗り心地が悪い」という感覚的な評価につながる場合もありますが、車内全体の静粛性や快適性は非常に高いレベルにあります。
結論として、「プリウスの乗り心地が悪い」という評価は、主に30系など旧モデルの特性に起因する過去のイメージであり、特にTNGAプラットフォームを採用した現行モデルにはほとんど当てはまらないと言って差し支えないでしょう。
プリウスミサイルへのトヨタの見解

相次ぐ事故報道や「プリウスミサイル」という極めて不名誉なスラングの拡散に対し、製造元であるトヨタ自動車の見解は、公式な場で一貫して示されています。
まず、トヨタは様々な事故調査に全面的に協力した上で、公式に「車両に構造上の欠陥は確認されていない」という立場を明確にしています。例えば、社会を震撼させた池袋暴走事故の際にも、トヨタは車両データを詳細に解析し、ブレーキシステムなどに異常はなかったとコメントしており、事故の主たる原因はあくまでドライバーの誤操作であるとの見解を示しました。
その上で、トヨタは自動車業界のリーディングカンパニーとして、この問題を社会的な責任と捉え、真摯に向き合っています。2019年に開催された株主総会では、当時の副社長が登壇し、相次ぐプリウスの事故について株主や社会に対して心配をかけたことを深く陳謝しました。そして、「安全なクルマ社会の実現のために、我々にできることはすべてやる」と力強く述べ、安全技術の開発をさらに加速させるという断固たる姿勢を明確にしたのです。
風評を払拭するための具体的な対策
-
- 先進安全機能の強化と普及:アクセルの踏み間違いを検知して加速を抑制する「急アクセル時加速抑制機能」を急ピッチで開発。新車への搭載だけでなく、旧モデルにも後付け可能な装置として販売し、普及に努めています。
– 新型車における根本的な設計変更:最新の5代目プリウスでは、長年誤操作の原因として指摘されてきた電子式シフトレバーを、より直感的に操作できる一般的な形状のシフトバイワイヤ方式に変更しました。さらに、ペダルの踏み間違い防止に効果が期待される「オルガン式アクセルペダル」をトヨタとして初めて採用するなど、ヒューマンエラーを減らすための設計を随所に取り入れています。
このようにトヨタは、単に風評を否定するだけでなく、その背景にある問題を真摯に受け止め、具体的な技術開発と製品改良を通じて、より安全な車社会の実現に向けて全力で取り組んでいるのです。
「プリウスミサイルは不謹慎?知らないと恥をかく言葉の誤解と真相」のまとめ
- プリウスミサイルは実際の交通事故を揶揄する言葉
- 被害者や遺族の感情を考えれば不謹慎と言える
- 言葉の元ネタは高齢者による事故報道の多発
- 特に池袋暴走事故が拡散の大きなきっかけとなった
- プリウスの事故が「多い」と感じる主因は販売台数の多さ
- 実際の事故率は他の車種と比べて突出して高くない
- 危険運転のイメージは静粛性や特殊な操作性が一因
- 高齢ドライバーに人気なことも事故が目立つ背景にある
- プリウスはデータ上では高い安全性能を備えている
- 悪い評判やイメージは報道やSNSの影響が大きい
- 乗り心地が悪いという評価は主に旧モデルの特性
- トヨタは車両欠陥を否定しつつ安全技術を強化している
- 言葉の背景にある社会問題を理解することが重要
- 単なるネットスラングとして軽々しく使うべきではない
- この言葉はトヨタへの風評被害にもつながっている
【必見】知らずに下取りに出すと100万円損するかも?




「長年乗ったし、下取りはこんなものかな…」と諦める前に、まずはWEBで最高額を確認してみてください。
-
6万キロのRAV4:下取りより80万円アップ!
-
9年落ちのハリアー:下取りとの差額は107万円!
驚くべきことに、これらはすべて「事前にWEB上で最高額がわかった」結果です。 1,500社以上の中から最大20社が競い合うため、ディーラーでは出せない驚きの査定額が算出されます。
車検前やローン中、残クレの途中でも全く問題ありません。まずは今の愛車の「本当の価値」を知ることから始めてみませんか?
※査定申込時の入力内容と実写の状態が異なる場合は減額の可能性があります。
※個人の感想であり、実際の査定・売却額を保証するものではありません。






